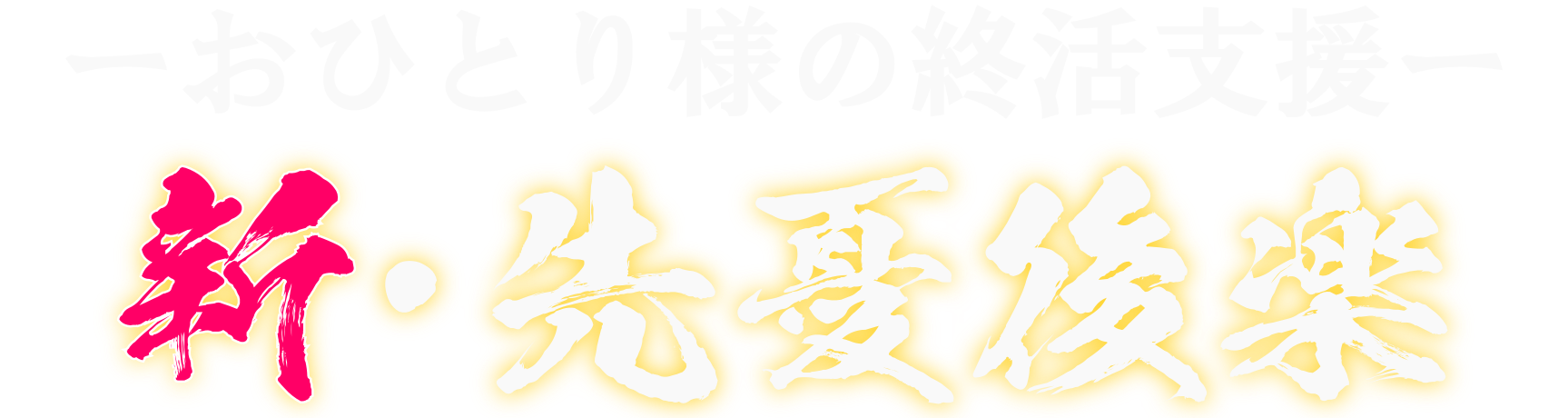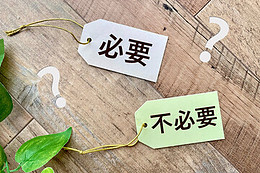
【はじめに】
先日受講した研修の中で
マイナンバーカードの現状と将来という項目がありました。
今日はその中から身近な問題となる様な項目に絞って
簡単に紹介したいと思います。
【順調な交付枚数・保有枚数】
研修資料によりますと、
マイナンバーカードの交付枚数は今年の1月末時点で
なんと1億枚を超えて人口に対する保有枚数率では77,6%と
ほぼ8割に達する状況とありました。
つい2,3年前まではようやく過半に達した等、
なかなか進捗が思わしくないといった記事ばかりが目立っていましたが
今ではここまでの浸透となりました。
さらに何かと話題になった健康保険証としての利用登録は
2024年末時点で既に83,7%にまで達しており
公金受取口座の登録でも66,0%と伸長が目立ちます。
これまで長くお世話になってきた紙の保険証は
昨年12月2日以降は新規発行がなくなり、
健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードが
基本となる仕組みに移行します。
ただご存じのように現状有効期限が残る既存の保険証は
有効期限までの間、最長で1年間は今まで通りの使用が可能ですし
何らかの事情でマイナ保険証を所有していない方には
新たに用意される「資格確認書」で資格の有無の確認がされます。
マイナ保険証に対応可能な医療機関や薬局も
交付枚数等に比例して導入が進んでおり
今年の1月時点で医科の診療所では8万軒以上、
歯科診療所や薬局でも6万軒以上で対応可能となっているようです。
導入当初は
マイナカードの利用出来るサービスが追い付いていない、
カードの取得は時期尚早では?
または失敗に終わった住基カードの二の舞になるのでは
といった懐疑的な見方が多かったものですが、
ようやく利用上のメリットを感じられる環境になりつつある?
これが令和のマイナカードの現状のようです。
【マイナ保険証のメリット】
ここではマイナ保険証になることのメリットを考えてみましょう。
まずは、手続きの簡便化が挙げられます。
医療機関の「窓口での高額療養費の限度額を超える支払の手続き」
がなくなります。
また、確定申告の際には
マイナポータルで医療費控除の手続きがスムースに
行えることも手続きの簡便化の一環と言えるでしょう。
次にメディカルデータの共有による
効率化と情報の正確性のアップでしょう。
自身の医療情報の提供に同意すると、
他の病院で診療した結果を含めて
今までの診療歴や健康診断の結果を
医師や薬剤師に正確な情報として
確認することが可能になるようです。
投薬の場合では
最新の薬剤情報が確認可能になるので
併用禁止の薬の確認や重複投薬を避けることに繋がります。
救急車などでの緊急搬送時にも
マイナ保険証の提示によって過去の診療情報や
薬剤情報を救急隊に正確に共有することが可能になるようです。
既にアンドロイドスマホでは
スマホにマイナ保険証の搭載が可能になっているとのことで
iPhoneにもこの春には搭載可能になる見込みとなっています。
これでスマホがあれば同時に保険証も携帯することになり、
医療機関や薬局でスマホの提示で保険証の確認が可能になります。
私は仕事上不意の外出や終日の外回りがあるので
常に紙の保険証を携帯して外出する習慣になっています。
ですが、隣近所のコンビ二やスーパーに行くだけの場合、
多くの場合、わざわざ紙の保険証を携帯して出かける人は
少ないのではないでしょうか?
この外出のタイミングで事故や急病となればそのまま搬送です。
おひとり様であれば自宅から保険証を持って来てくれる家族もいません。
ですが今やシニア世代でもスマホは肌身離さずといったケースが
一般的になってきています。中には自宅のトイレにも持ち歩くといった
身体の機能の一部のような扱いをしているシニアもいるようです。
こういう場合にスマホ一体型の保険証を用意しておけば
いざという場合に我が身を扶けてくれるツールとなる訳です。
【マイナンバーカードと運転免許証の一体化】
そして今日、3月24日より運用が開始されるのが免許証との一体化です。
これによって免許証は以下の3形態に分類されることになります。
1)今まで通りのカード型の免許証のみ
2)マイナ免許証のみ
3)双方を所有
これに合わせて
この2月1日からは免許の更新は予約制に移行されました。
今までのように唐突に「今日は暇になったから」と
急遽免許更新に出向くといったことは出来なくなりました。
マイナ免許証のメリットとしては
優良・一般運転者に関しては、
必要な手続きをとった場合に
免許更新に必要な講習を「オンライン講習」での受講が
可能になります。
また更新に伴う手数料に関しても
先の3つの形態によって異なる料金体系になるようです。
1) 新規取得手数料
運転免許証のみの場合は 2,350円
マイナ免許証のみの場合は 1,550円
両方保有の場合は 2,450円
2)更新時手数料
運転免許証のみの場合は 2,850円
マイナ免許証のみの場合は 2,100円
両方保有の場合は 2,950円
あきらかにマイナ免許証優遇策となります。
また転勤や転職などで住所変更となった場合、
その届出は警察署での手続きでしたが、
マイナ免許証のみの場合で必要な手続きをとった場合には
役所での手続きだけで済み、警察署に出向く必要がなくなります。
以上を見ますと
やはりマイナ免許証への優遇が見て取れますね。
とはいえ、
取得・更新時の手数料は前者は普通1回限り、
更新も数年に一度発生するだけの費用です。
これが毎月・毎週発生する費用となれば
その格差は大きな意味を持ちますが、
数年に一度、1,000円以内の差額ですから
そこまで切り替えのメリットとは感じないのでは?
気になるのは仮に免許証の盗難や紛失、
あるいは破損の場合の再発行までの日数と費用です。
マイナ免許証の再発行の際には
まずマイナンバーカードの再発行が必要で
これが概して最短でも1週間はかかるとのことでした。
当然再発行には手数料が発生します。
またマイナカードが再発行された後にも手続きがあります。
その後は免許情報をマイナカードに一体化する作業となります。
新規の一体型免許証が手元に届く前に運転してしまえば
即「免許不携帯」で交通違反の対象となってしまいます。
詳細は省きますが、
再発行時の手数料でマイナ免許証は割安の設定で
概ね千円前後安く再発行が出来ます
(従来の免許証や2枚持ちの場合と比べ)
ですが
費用面の問題より切実なのは再発行までの時間でしょう。
特に商売上毎日運転をするような職種の場合、
この所要時間の問題は致命的です。
まず平日の開庁時間内に自治体窓口に出向き
マイナカードの再発行手続きをして最短でも1週間は
じっと我慢、再発行された後は、今度は警察での手続きで
免許情報のマイナカードへの一体化の作業を済ませることで
ようやく再びハンドルが握れるようになるのです。
要は
再発行する事態を招かなければいいだけの話ではありますが、
万が一、再発行する場合には所要時間の問題を覚悟しましょう。
【マイナカードとスマホの一体化】
昨年5月成立の改正マイナンバー法によって
マイナカードと同等の機能をスマホに搭載、
マイナカードを持ち歩く必要を無くし
スマホでの本人確認が可能になるようです。
具体的には基本の情報
(氏名、生年月日、性別、マイナンバー、顔写真)を
スマホに搭載し、マイナカードの電子証明書機能と併せて
本人確認が可能になるというものです。
スマホでも盗難、紛失のリスクはありますが、
カードの持ち歩きよりは注意力も意識も向いているはずで
その(盗難・紛失)リスクは大幅な減少が期待出来ます。
とはいえ不安な要素も無い訳ではありません。
スマホが充電切れや機械的な不具合によって機能不全となれば
他の機能同様マイナンバーカードとして使用も不可になるでしょう。
一極集中の便利さとそれに比例する危険性は避けられません。
【終わりに~次の課題】
冒頭に紹介したようにマイナンバーカードの発行枚数は
着実に増加しています。ではその活用度合いはどうでしょうか?
2024年度の意識調査によれば
デジタル行政サービスを一度でも利用したと答えたのは
全体の約6割だったそうです。
ですが今後も行政サービスを利用したいと回答したのは
利用したいは約38%、どちらともいえないが約42%で
積極的な利用度合いという点では今一つのようです。
社会のデジタル化をどう思うか?
という問いかけについては約51%が良いと答え
自分は社会のデジタル化に適応出来ているか?
については、出来ているは30%未満、
デジタル行政サービスに満足しているか?
については、こちらもYESは30%未満でした。
昨年11月のノートン社の調べによれば
マイナカードの携帯率は約50%、
使用目的としては「身分証明書」としているのが
やはり約50%となっているとありました。
カードは財布などに入れて持ち歩くが53%
盗難や紛失でカードを第三者に不正利用される可能性を懸念が
これも約50%となっているようです。
根幹であるカードの制度上の不安感も依然として根強いようで
・管理体制の不透明、
・過去の情報漏洩の事故、
・個人情報保護に対する規制不十分
等の点からマイナンバー制度自体を信用していない
という声もでているとのことです。
カード作成の理由のトップは、
依然として「マイナポイント」で約52%
「利便性」を回答したのは僅か10%強でした。
どうにも未だに
導入当初から囁かれてきた安全性への不安の問題は
完全には払しょく出来ていないといえるでしょう。
冒頭にメリットとして採り上げたマイナ保険証でも
読み取り機の問題かカードの不具合か、受付不能となり
来院者に予期せぬ負荷をかけることが今もニュースになる始末です。
スマホ一体化についても情報の一極集中によるリスク、
スマホの不具合で全ての情報(身分証明を含め)開示が
不可能になるリスクは機械ものである為皆無にすることは困難です。
無論、
持ち主の不注意での盗難や紛失、破損等は
あくまでも自己責任ですから
一極集中のツールを取り扱う責任感は
十分自覚しなければいけません。
一気に集約することを良しとするか?
当面は既存の(アナログな)サービスとの併用を堅守するか?
特におひとり様の場合、
スマホはより重要なデジタル遺品になります。
個人情報の「保管庫」となれば暗証やロック解除には
それ相応にセキュリティを考えるでしょう。
仮に免許証も保険証も紙でなく
スマホ内のマイナンバーカードに集約されていたら?
自宅以外の場で何かアクシデントがあり
自身で受け答え出来なくなった場合に
従来のように携帯していた免許証や保険証での確認と言った
本人確認や身元照会はかなり困難になるのではないでしょうか?
マイナカードの現状をよく把握して、どちらを選択するかは
あくまでも個人の自己責任となることを肝に銘じて下さい。
この記事の著者

- 寺田淳行政書士事務所 代表
-
東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
■フェイスブックページ「50歳からの人生設計相談室」
■ブログ「新・先憂後楽」
■コラム「マイベストプロ東京」
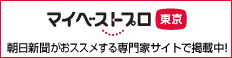
最新の投稿
 50代2026年1月25日一人になる、独りにされるの違い
50代2026年1月25日一人になる、独りにされるの違い これからの人生2026年1月5日シニア世代の転倒事故について
これからの人生2026年1月5日シニア世代の転倒事故について おひとり様2025年12月25日2025年を振り返って
おひとり様2025年12月25日2025年を振り返って シニア世代2025年11月28日貴方はいつ終活を意識しましたか?
シニア世代2025年11月28日貴方はいつ終活を意識しましたか?