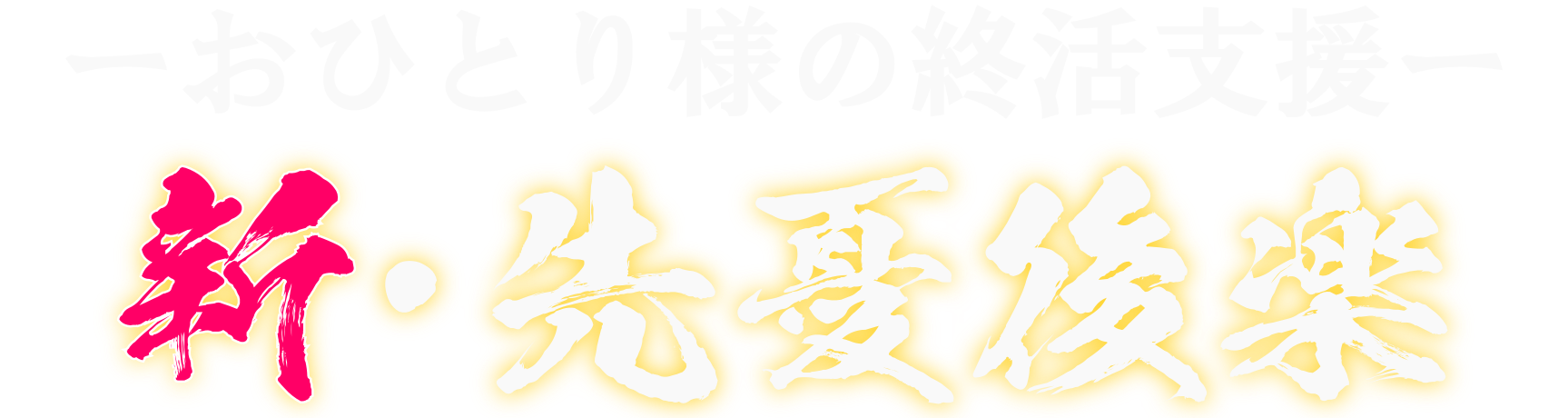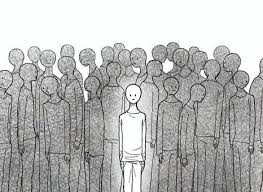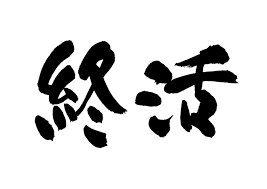
【はじめに】
先日、テレビの情報バラエティ番組の特集で
終活の準備を始めたのは何時から?
という調査の結果が採り上げられていました。
それによりますと、第一位は70代からで
私自身の考える60代からではありませんでした、
さらに第二位に関しては60代、ではなく
なんと心身充実のはずの20代が僅かですが60代を上回って
年代別の第二位という結果でした!
その割合は約26%、
20代の約1/4が早々と終活を開始しているとのことでした。
この後も同様の情報番組で20代の終活が採り上げられていました。
今日はこの件について紹介したいと思います。
【20代の終活準備】
この調査によりますと
具体的にどんな終活の行動をするかという問いには
遺言書の用意、遺影の用意、親しい友人へのメッセージ
この3つがそれぞれ10%で第一位でした。
友人へのメッセージはまだしも
遺影迄用意というのはかなり違和感を覚えましたが、
背景には近年の天災やコロナ禍といった災厄を体験することで
昨日まで元気だった先輩や同僚、後輩、友人、兄弟がもういない。
若くても死は平等にやって来るという一種の諦観、死生観からの行動
ではないでしょうか?
私自身も概ね同じ考えで、老若男女関係なく「お迎え」は来る。
だから悔いのない備えは今日からでも取り組むべしと言ってきました。
テレビという公共の場でこの様な問題提起が行われたこと自体、
私が最初に終活を意識した15年前と比べ、大きな前進と考えます。
【遺言書の作成】
以前から私見として
遺言書の作成は私はこれまで家庭を持った時、
または子どもが出来た時が第一のチャンスと考えています。
基礎中の基礎ですが子のいない夫婦の場合、
相続権の問題から故人の親族(原則親兄弟)と遺された配偶者間で
「争族」が発生するリスクがあります。
※子供がいれば親兄弟に相続権は生じません。
不毛のリスクを回避するためにも、
結婚したらお互いが遺言書を用意することで
無用な遺産相続のストレスを避けるべきと思うからです。
今回の調査では
20代で終活準備を始めた方の家族構成は
明らかではなかったですが
上記のような結婚していてまだ子のいない夫婦や
子供が誕生した場合には20代での「最初の」遺言書作成は
トラブル予防の観点からも私は大いに推奨します。
【遺影の用意】
気にかかるのは二番目に挙げられた「遺影」ですが
今の時代、スマホには大量の自身の写真や友人との写真が
溢れかえっているはずです、特に20代であれば。
改めて遺影の撮影に専門家に依頼せずとも
大量のストックの中からお気に入りを選んでおけば済みます。
遺言書でも言えることですが、
早々と遺影を用意して、その後長寿に恵まれた場合には
当然ながら実物とギャップが生じます!
定期的な更新という習慣も身に着けておかなければ
いざ本番の葬儀の際に20代の写真しかないという問題が生じます。
事実80代の方の葬儀の際の遺影が30代の頃のものであり
かなり違和感を感じた経験を私自身しています。
遺影に関しては、出来ればプリントアウトしておけば
迅速な対応も可能ですので1年毎に撮影し印刷しておけば
これはこれで一種のライフログにもなります。
余談なりますが、
遺影に関しては年代を問わず、
まずは健康な状態の時に、
笑顔、破顔一笑といった表情の写真が好ましく思えます。
また多くの場合、40代から60代にかけての
壮年期の笑顔の写真を遺影に選択するケースは多く
この時期の「ベストショット」が得られれば、
毎年の遺影撮影は打ち止め、でいいのではと思います。
【友人へのメッセージ】
あくまでも20代でのメッセージとなれば
まだ新鮮な思い出である学生時代や新入社員時の友人、
幼馴染の知人らが対象でしょう。
楽しかった出来事や思い出の出会いなどを綴るのも結構ですが
物品や金銭の貸し借り等は必須案件として意識しましょう。
私もそうでしたが、友人間の貸し借りに覚書を交わしたり
文字として記録することはまずありません。
ただ口約束だけで済ませた場合、
実際に亡くなった後の返却がかなり面倒なことになります。
「これは私が彼に貸していた本です、DVDです、服です。」
と主張してもその事実を知らされていない遺族からすれば
「はいそうですか、ではどうぞ」にはなりません。
特に金銭の場合は下手をすれば深刻な不信感を生じさせます。
美しい思い出だけで終わらせるのではなく、
周囲に迷惑をかけない配慮もメッセージには込めて欲しいものです。
【注意事項として】
60代、70代でも何も終活に向けての準備をしない方もいます。
それに比べれば20代で終活を意識し、具体的行動を始めるというのは
大いに推奨したい事です。
ですが、注意点としては
通常の生活を続ける中では20代で終活の準備全て完了とはいきません。
ここに挙げた3つの終活にしても
その後の人生の中で遺言書の内容に変化が生じることや
遺影に関しても年相応の画像に切替えなければ前述したように
葬儀の場で遺族に迷惑をかけるリスクが出てきます。
メッセージにしてもその後疎遠になったり決裂したケースは
少なくありませんし、その後の出会いで終生の友と巡り合うことも
また当然のように発生します。
変な言い方ですが、60代以降になれば
顔かたちの変化もそうはないはずですし、
遺言書の内容にも大きな変動が生じる可能性は減少してます。
メッセージもごく少数の真の友人宛に遺すものになり
修正や削除、追加の可能性も極めて少なくなります。
さらに言えば、
まさか20代で「生前整理」「断捨離」を完了する訳はなく
終活自体はそれこそ最期の時、または70代以降まで続くもの
と考え、じっくりと取り組まなければいけません。
最後に、今の時代個人情報の大半を自宅のパソコンや
スマホに集約するケースは珍しくもありません。
内容が完璧なモノであっても
その存在を家族や第三者に知らせていなければ
闇に葬られるだけですし、仮に存在は伝えていても
IDとパスワードを伝えていなければ結果は同じです。
遺言書やメッセージは紙に書いて保管することも出来ますし
遺影に関してはプリントアウトしておけばそのまま流用出来ます。
ですがどう保管し、その事実を誰に伝えるかは
なかなかに難しい問題ではあります。
終活の用意をすることも大切ですが、
より問題なのはその内容、事実をどう保管し
どう伝えるか、なのです。
【終わりに】
ご存じの方にとっては当たり前のことですが
遺言書には法的な効力を有する為の型式があります。
この点をよく理解しないまま
自前で遺言書(もどき)を作成しても
遺された家族にとっては無意味な存在でしかありません。
遺言書作成の相談などはネットに依存せずに
信頼出来る専門家に相談することをお薦めします。
最後によりシビアな問題として2つ挙げておきます。
まずは「おひとり様の終活」です。
20代で正真正銘のおひとり様というケースは
少ないとはいえ存在はしています。
こういう場合、先に紹介した遺言書や遺影は
誰に向けるものかを考えておく必要があります。
次が「判断力喪失」のケースです。
五体は満足でも意識不明での入院や
所謂認知症で日常生活が困難なケースも
20代で考えておくべき問題です。
残酷な話ですが、このケースの場合
遺影や遺言書は存命中には意味のないものです。
そうなれば、後見人、後見制度についても
終活の一環として認識する必要が出てきます。
特におひとり様の場合はその時が来る前に
後事を託せる友人や士業従事者といった専門家との
連携を考えておかなければいけません。
私の周囲にいる20代30代の方々への聞き取りでは
遺言書、終活に認識はかなり高いものがありましたが
後見制度、後見人、任意後見契約等はほぼ皆無でした。
さすがに20代で認知症の心配は早過ぎといえますが
事故や脳の病気で事実上認知症と同じ様に判断力、
意思の発揮が出来なくなるケースはごまんとあります。
まさか自分が? というのもよく分かりますが
家族がいる場合でもその対応にはかなりの困難が生じるのです。
まして頼れる親族がいないおひとり様であれば…
自分の身は自分で守るではないですが、
あらゆる事態を想定することは無駄にはなりません。
死亡よりも難問である
「判断力の喪失しての存命の場合への対策」
特に、20代30代の若い世代にとって
この問題は今後の課題となると思います。
この記事の著者

- 寺田淳行政書士事務所 代表
-
東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
■フェイスブックページ「50歳からの人生設計相談室」
■ブログ「新・先憂後楽」
■コラム「マイベストプロ東京」
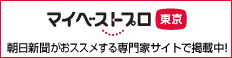
最新の投稿
 これからの人生2026年1月5日シニア世代の転倒事故について
これからの人生2026年1月5日シニア世代の転倒事故について おひとり様2025年12月25日2025年を振り返って
おひとり様2025年12月25日2025年を振り返って シニア世代2025年11月28日貴方はいつ終活を意識しましたか?
シニア世代2025年11月28日貴方はいつ終活を意識しましたか? おひとり様2025年11月4日かなり手間がかかる趣味品の終活:書籍類
おひとり様2025年11月4日かなり手間がかかる趣味品の終活:書籍類