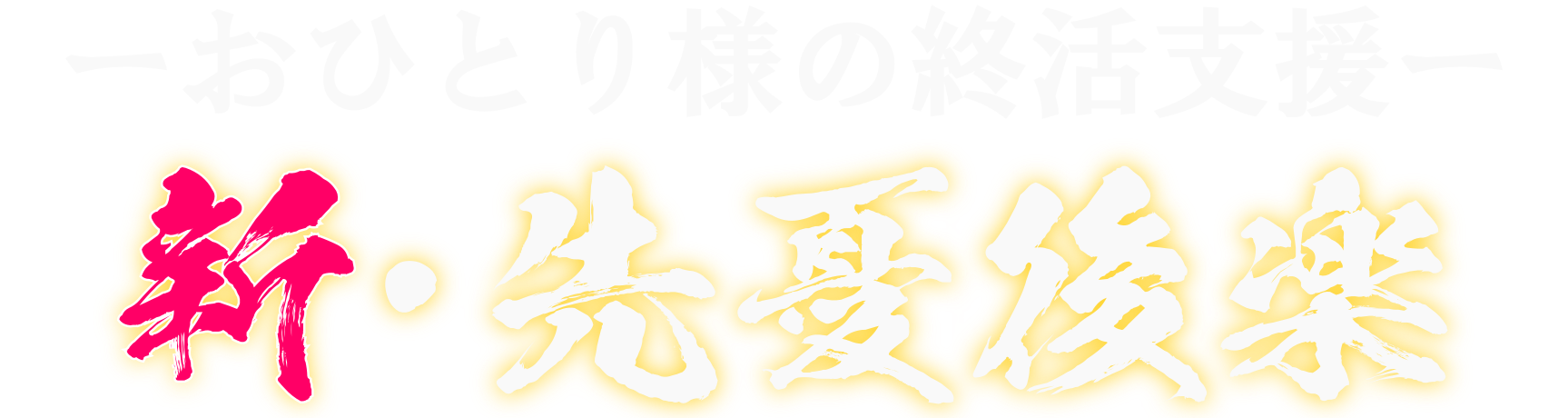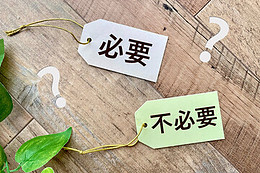【はじめに】
相続が発生した際に故人が口座を開設している銀行で
貸金庫を契約しているケースは少なくありません。
いろいろ問題が生じている貸金庫ですが、
やはりいろいろな事情で自宅保管ではどうもという場合、
貸金庫に重要書類等を保管する安心感は否定出来ませんね。
今日はこの貸金庫と故人名義の口座解約の手続きとの関係について
実際にみずほ銀行で経験した事例を基に紹介していきたいと思います。
【銀行口座の解約について】
例えば全国に拠点のある大企業に勤めている場合、
転勤に伴って銀行口座を変更することはよくあることです。
何らかの事情(単身赴任など)で元の住所地の口座を温存したまま
新たな赴任先住所地で同じ銀行で口座を開設するようなケース。
または自宅近くの支店と勤め先近くの支店の2か所に口座を開設するケース。
この様な事例は案外多く存在するようです。
ここに故人の子供も同じ銀行で(違う支店に)口座を開設していたとすると
同じ(みずほ)銀行で親子で3つの口座が存在することになります。
この様な状態で親が亡くなった場合、
親の遺した2つの口座の解約手続きはどうなるでしょうか?
相続人(配偶者や子供)は2つの支店の窓口に出向いて
それぞれ解約手続きを行わなくてはいけないのでしょうか?
まず、どちらか一方の窓口に出向けば他の支店の手続きも可能です。
さらに言えば、ここで採り上げたケースでは相続人である子供も
同じ銀行に口座を開設しています。
この場合には子供の口座が開設してある支店で
親の遺した2支店の口座解約の手続きが可能なのです。
先に書いたように、今や遠隔地になった以前の居住地に
残してしまった口座の手続きも、故人の勤務先近くの口座
(子の住まいからはかなり遠方というケースもあり得ます)
であっても自分の口座のある最寄りの支店で故人の名義の口座、
このケースでは2支店分を同時に解約が出来るのです。
但し、
故人が貸金庫契約を結んでいた場合は話は変わってきます。
【貸金庫の解約は契約した支店で】
故人がどこかの支店で貸金庫契約を結んでおり
今もその契約が継続中であればそうはいきません。
故人の口座解約手続きは貸金庫のある支店でしか出来ません。
仮に今は遠隔地となった支店に貸金庫を契約していたら?
既に中身は全て自宅に持ち帰っていたとしても
貸金庫の契約が継続中であれば相続の手続きはその支店が窓口になります。
現在こういった状況の親世代の方、
そういう話を聞いたことがある子供世代の方、
今もそのままであるならば、要注意です。
原則として貸金庫の解約は契約者本人でしか出来ません。
嫌な言い回しになりますが、契約者が人事不省になっていたら
相続発生までは手続きはかなり難しくなります。
もう重要な品が入っていないのであれば
契約者自身の健康状態に問題なければ
早々に当該の支店に契約者が出向いての解約手続きを推奨します。
昨今の行員による不祥事というニュースを見ても
もはや銀行の貸金庫だから100%安心安全という神話は崩れました。
最低限、今の時点で金庫内にはどういうものが保管されているか
正確な一覧を作成して親子共通の認識とすべきですし
何度か出し入れをしているのであれば現状を確認する為にも
一度親子(夫婦)で金庫の内容を確認することをお薦めします。
契約者が解約前に亡くなった場合、
相続人(相続人の代表者)が解約手続きを行うことになります。
この事例では幸か不幸か相続人は一人のみだったので比較的スムースに
手続きを進めることが出来ましたが、仮に複数の相続人がいた場合
まずは手続き実務を行う相続人代表者を決めなければいけません。
その旨を相続人全員が承諾しているという旨を記載する書類作成を行い
そこで初めて貸金庫契約がある支店に出向き、具体的手続きの開始となります。
ここで注意すべき点があります。
相続の手続きや貸金庫の解約は必ず来店予約が必要になります。
時間が空いたから、仕事の都合で近くに来たから等の理由で
予約なしに飛び込んでも受け付けてはもらえません。
事例では2月初旬に手続きを申し入れたところ、予約出来たのが20日過ぎで
2週間以上待たされることになりました。
特にタイミングが悪かったという訳でもないようで
一般的に1~2週間、繁忙期では3週間前後も予約が取れないとのことでした。
勝手に自分の都合だけで来店・手続きの計画を組んでも無意味ですので
まずは当該支店に来店を申し入れ自分の都合との調整を図るようにしましょう。
また相続の手続きに加えて貸金庫の解約手続きが加わりますと
概ね2時間は優にかかります。
聞いた話では14時以降の予約は難色を示します。
15時には一般業務は終了し、正面の入り口は閉鎖されます。
今回のケースでは13時半に予約して全て終了したのが15時半過ぎでした。
手続き終了後は非常口から退出したそうです。
予約には日程に加えて出来れば午前の予約を前提にした方が
余裕をもって対応が出来ると思います。
余談ですが、最初にカードキーと暗証番号で室内に入り
金庫内のケースの保管されているロッカーには鍵を差し込んで開錠し
中身を引き出す仕組みです。
解約時には当然このキーや鍵も返却するのですが
銀行のHPでは「カードキーは返却せずに破却して下さい」とあります。
ですが、当該支店との電話のやり取りでは「鍵と一緒に持参して下さい。」
と、対応に差がありました。
結局はどうせもう用無しになるので鍵と共に持参し返却したそうです。
たまたまその支店でのオリジナルルールだったのか?
この辺りは直接当該支店にそれぞれ確認をお願いしたいと思います。
【終わりに】
貸金庫の解約時には入り口まで行員が同席し
金庫内への開錠を行いますが保管物の確認には立ち会いません。
手続きに出向いた相続人が内容物の確認と回収を責任を持って行います。
事前に保管物の内訳が判明しているならば
一覧表などを作成しておけば時間短縮にもなりますし
他の相続人に変な疑惑を持たれずに済みます。
内容物が全く分からないような場合な
個人的には複数の相続人での手続きがいいのではと思います。
仮に金庫室への入室が一人と限定された場合でも
待機した相続人が退室直後の相続人が回収した内容物を
その場で確認出来ることで疑惑の目を摘み取ることになります。
以上、経験談を基に手続きのポイントを紹介したつもりですが
やはり契約者本人が解約するのが最も手っ取り早く完了すると
改めて確信しました。
昭和の時代はまだ株券や有価証券等が紙の現物でしたので
貸金庫の重要度は高いものがありましたが今やそれらは全て電子化で
ペーパーレスの時代になりました。
ここで問題になるのが「現金の預け入れ」です。
各行のHPに掲載されている規則では「保管できるもの」「保管できないもの」
が具体的に掲示されていますが、現金はそのどちらにも記載されていません。
出来るものでもなく、出来ないものでもない? 非常にグレーな扱いです。
ここでは建前として「現金はなし」という前提で考えますが
そうなりますと残るのは金庫で保管するに値するものとして
貴金属類や、遺言書が思い浮かびます。
特に遺言書の場合、まず遺言書の内容を把握してから
次の行動の優先順位を決めることがありますが、
貸金庫の解約が出来なければ手続きを進めることが出来ません。
もっとまずいのは遺言書の有無が判明していない場合です。
仮に遺言書があると考え、遺産分割協議をせずに待機したものの
実際は無かったとすれば貴重な時間を空費することになります。
逆に遺言書は無いと考え、先に分割協議を進めていた場合、
遺言の内容いかんでは相続人の中から協議内容の見直しを主張します。
既にみずほ銀行では新規の貸金庫の受付を停止したというニュースも
入ってきた中、いずれは貸金庫自体を全廃するのではないでしょうか?
繰り返しますが、現在貸金庫を利用している方は
これらの状況をよく考えて、今後の終活に役立てて欲しいものです。
この記事の著者

- 寺田淳行政書士事務所 代表
-
東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
■フェイスブックページ「50歳からの人生設計相談室」
■ブログ「新・先憂後楽」
■コラム「マイベストプロ東京」
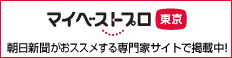
最新の投稿
 シニア世代2026年2月20日せん妄について
シニア世代2026年2月20日せん妄について シニア世代2026年2月5日高齢者の運転免許返納について
シニア世代2026年2月5日高齢者の運転免許返納について 50代2026年1月25日一人になる、独りにされるの違い
50代2026年1月25日一人になる、独りにされるの違い これからの人生2026年1月5日シニア世代の転倒事故について
これからの人生2026年1月5日シニア世代の転倒事故について