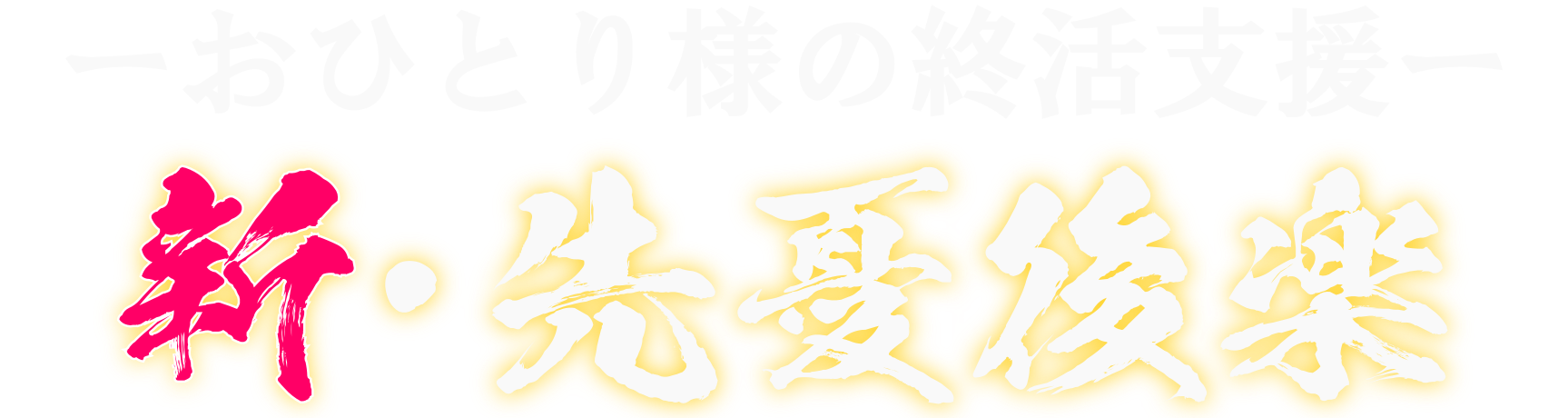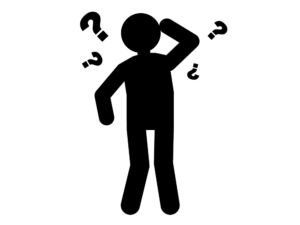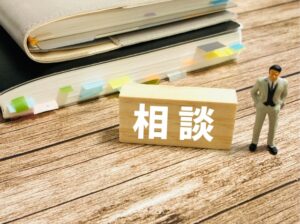
【はじめに】
今回の話は旧友が父親の死去に伴って
実家の土地と遠隔地にある父親名義の土地を相続する際に
直面した一種のドタバタ劇です。
とはいえ、多くの方にとっても
これは知らなかった!だけでは済まない場合もあると思い
今回この場で紹介することとしました。
結論、日本の税制は実にややこしい!?
【固定資産税非課税の土地だった!】
彼が亡父の葬儀を済ませ相続の準備に取り掛かった際に
不動産には固定資産税がつきもの、課税の通知書が保管されているはずだから
まずは書類の調査からとなり、生前に確認していた田舎の土地に関する書類を
家中探したものの見当たらなかったそうです。
(山陰の)土地の存在だけは聞いていた(または覚えていた?)ので
最後は管轄の自治体に問い合わせたところ、課税対象外の土地と言う
回答が届いたそうで、だから実家にも課税通知が届かなかった訳です。
「これから使い道のない土地に毎年税金を払うのかと思い込んでいたけど
非課税の土地だったんだ、後は名義変更するだけで済む!」
と、当初は喜んでいました。
後日手続きをした際の登記申請書にも
課税評価額 0円 固定資産税 0円と記載されており
本人としては田舎の土地問題はこれで一件落着、のつもりでした。
【固定資産評価額は固定資産評価証明書で確認】
さて今回、固定資産税は非課税でしたが
あくまでも相続財産(不動産)なので
相続税の課税対象にはなります。
彼は完全に固定資産税非課税で課税0円=固定資産の評価も0円
と思い込んでしまい、申告書の作成を進めたのです。
その後、彼と雑談の機会があり、その中でこの件の話題となりました。
話を聞いていてどうも勘違いしていると感じた私から
「固定資産評価証明書」の取得と評価額の確認の有無を尋ねました。
案の定、そこにはしっかり価額が記載されていました。
さらに土地の中の1か所の地目が山林だったことで
課税額の算出が路線価ではなく倍率法の適用となり、
自治体による倍率が「23倍」に該当することが分かったのです。
ご存じの方も多いと思いますが
一般的に自宅などの場合、
殆どの市区町村では「路線価」で評価額を算出しますが、
田舎の畑や山林などは「倍率法」が適用され、
税額が算定されます。
路線価や倍率法について詳しく知りたい場合は
国税庁のHPをを参照してください。
双方のサイトが用意されていますので該当するサイトで確認しましょう。
彼の場合評価額はさほどでもなかったのですが
適用される倍率によってそれなりの金額になっていました。
当然、申告書の不動産に関する箇所の再計算をすることとなり
当初の提出予定日はいったん取り止める羽目となったのです。
ただ彼の場合、これだけでは済みませんでした…
【介護施設等入所後の小規模宅地の特例の適用】
2つ目は亡父が暮らしていた実家に関しての問題です。
彼の亡父は長年ひとり暮らしを続けており
事故による入院から3か月後には介護施設への入所が余儀なくされました。
ですが入所して僅か4か月で体調が急変して亡くなったそうです。
配偶者(母親)はすでに亡く、相続人は自分ただ一人、
土地の面積も「小規模宅地の特例」の基準内と言うことで
当然ながら田舎の実家の土地に関して特例適用の申請を作成したのです。
が、ここでも彼の勘違いが2つありました。
まずは事故や病気で入院した先の医療機関での死亡であれば
手続上何の問題も無かったのですが、今回は4か月とはいえ
自宅から居住地を介護施設に移したという事実があります。
税務署の判断では病院への入院は自宅に帰還が前提、
介護施設への入所は自宅帰還は出来ないという前提で
手続に相違があるということです。
彼のケースでは以下の書類の添付が求められました。
1)故人の戸籍の附票
2)入所施設との入所関係の契約書の写し
3)介護保険被保険者証の写し
4)障碍者認定の通知書の写し
上記の4点を添付することで特例の対象に該当と
判断されるという回答で大慌てで書類を取り寄せたのです。
これで特例適用の為の
「亡き父親」の必要書類は完成したのですが…
【家なき子の小規模宅地の特例の適用】
3つ目のドタバタ劇は彼自身の「家なき子の証明」でした。
小規模宅地の特例には「同居人であること」が条件の一つに
挙げられていますが、2018年の税制改正により「家なき子」
の場合でも特例の適用が認められるようになったのです。
彼は現役のサラリーマンで転勤族です、
実家には大学卒業以来住民票を移して以降居住したことはなく、
会社の方針?で3~4年での転勤が常態化していることもあって
今に至るまで「賃貸暮らし」で持ち家経験はゼロ。
いわゆる「家なき子」で過ごしてきたのです。
そこまでは彼も事前に知っていたので、
先に述べた案件の中でも同居はしていないが
家なき子だから適用対象だと認識していました。
ですが小規模宅地の特例の適用の為には
「家なき子」の証明 が必要なのです。
幸か不幸か、彼は一人息子で唯一の相続人。
他の相続人に迷惑をかけることはなかったのですが
この問題発覚で都合3回の申告の延期となりました。
家なき子の場合は
相続の発生前3年間、
自分の所有する住宅に暮らしていなかった
という条件を満たす必要があります。
その為現在の賃貸物件との間で交わした
賃貸契約書の写しも添付しなくてはいけなかったのです。
先に述べたように彼は一度も持ち家経験はなく
今の賃貸マンションには10年近く暮らしているので
このマンションとの賃貸契約書を添付することで
ようやく全ての必要書類を用意出来ました。
余談ですが、
10年前の賃貸契約書、保管場所を覚えている訳もなく
その捜索に丸一日がかりだったそうです!!
皆さんも何かあった時の為に重要書類等の保管場所は
常に最新の状態を把握しておいて損は無いと思います。
【終わりに】
本人にとっては苦労の連続だったようですが、
我々にとっては貴重な教訓を得るいい機会を与えてくれました。
相続の手続きにはいろいろな注意事項がありますが、
その中でも特に注意すべきは記述したような固定資産非課税の土地等です。
祖父からも父からも、二代にわたって
(土地について)何も聞かされていなかったというある相談者は
相続手続きと連動して隣接する代々の菩提寺の墓じまいを行い
菩提寺の住職との面談の際、初めてこの手の土地の存在を聞かされたという
全くの偶然によって申告書の記載漏れを未然に防げたと言っていました。
全く故意でなかったとしても
後になって土地の存在が国税に発覚すれば?
故意に隠したのでは?と疑われても仕方ありません。
今回のケースでは手続きの3度のやり直し
と言う程度の「損害」で済みましたが
一歩間違えれば税務調査の際に
相当な時間をかけての釈明が必要になるかもしれません。
ですから他の相続関係の手続きと同じく、いやそれ以上に
不動産に関しては事前の調査や情報の収集の徹底が不可欠です。
貴方は将来相続するであろう財産の中に
不動産はありませんか?
あったとしてその価値や名義等は全て把握出来てますか?
この記事の著者

- 寺田淳行政書士事務所 代表
-
東京は新橋駅前で「寺田淳行政書士事務所」を開業しています。
本業では終活に関連する業務(相続、遺言、改葬、後見、空家問題等)を中心とした相談業務に従事し、さらにサラリーマンからの転身という前歴を活かした起業・独立支援に関する支援業務やセミナー講演等を開催して、同世代の第二の人生、第二の仕事のサポートも行っています。
主に以下のSNSで各種情報を随時発信しています。
■フェイスブックページ「50歳からの人生設計相談室」
■ブログ「新・先憂後楽」
■コラム「マイベストプロ東京」
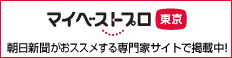
最新の投稿
 シニア世代2026年2月5日高齢者の運転免許返納について
シニア世代2026年2月5日高齢者の運転免許返納について 50代2026年1月25日一人になる、独りにされるの違い
50代2026年1月25日一人になる、独りにされるの違い これからの人生2026年1月5日シニア世代の転倒事故について
これからの人生2026年1月5日シニア世代の転倒事故について おひとり様2025年12月25日2025年を振り返って
おひとり様2025年12月25日2025年を振り返って